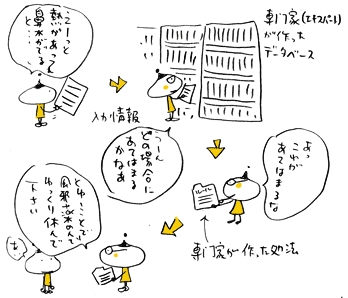人工知能の歴史・理論と技術 4
続いて、第2次AIブームに入ります。これに関しては、日本がきっかけを作ったようなところがあります。1982年に経済産業省の肝煎りで「第5世代コンピュータプロジェクト」が始まりました。並列論理型言語を実行するコンピュータの開発と自然言語の理解などを目標とし、人工知能を目指すものとして一般には報じられました。これを受けて、世界各国で「AI分野における日本の先行を許さじ」とばかりに、AI研究が復活していったのです。
1980年代初頭 エキスパートシステムが隆盛しはじめる
大規模データベースの運用方法研究の延長で、人工知能の一形態であるエキスパートシステムがさまざまな分野で構築され、利用されるようになりました。
エキスパートシステム
E. ファイゲンバウムらが1960年代から開発していたエキスパートシステムですが、1980年代にビジネスの場面で、さまざまな分野に限定的に特化するものがさかんに利用されるようになりました。
エキスパートシステムの先駆的なものにはDendral(1965)やMycin (1972)があります。前者は分光計の測定結果から対象物質を特定するシステムで、後者は感染性血液疾患の病原菌を特定し、回答できるものでした。
Mycinは、「グラム陽性ですか?」、「好気性ですか?」、「形は桿状ですか?」など「はい/いいえ」または簡単な文章で答えられる質問を医師に対して投げ、その答えを積み重ねていく中で病原菌種を絞り込んでいきます。最後に確率の高い順にいくつかの病原菌種を回答し、回答の理由と推奨する治療方針まで出力しました。その的中率は65%ほどで、専門医の80%には及ばないものの、一般開業医の成績は上回っていました。かなり成功したと言えるのですが、「コンピュータを医療に使って間違った診断を下した場合、誰が責任を取るのか」という議論があり、その後はまったく使われなくなってしまいました。
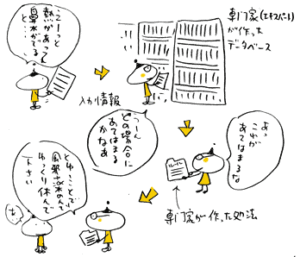
https://www.1101.com/morikawa/2001-05-09.html
さて、Mycinのようなエキスパートシステムは、「もし……なら……」というデータ形式の知識ベースを持ち、その数百から数万にもおよぶ規則を検索していくことで、専門家による観測から判断までの過程を再現する仕組みになっています。
アキネーター
身近なところでエキスパートシステムを体験できるものとしては「アキネーター」があります。ダウンロードせずにブラウザで実行できるものもあるアプリケーションで、ユーザーが思い浮かべた人物やキャラクター(実在の人物でなくてもよい)を、いくつかの質問に答えるとアキネーターが言い当てるというものです。
先ほど「額田王(ぬかたのおおきみ)」で試してみたところ、かなり手こずっていたようで、15問ほどの質問に答えたところで「持統天皇」と、かなり惜しい回答があり、「ちがう、続けて」と指示すると、さらに5問ほどの質問に答えたところで正解を出しました。さらに、「ロケットニュース24」の佐藤英典(さとうひでのり)記者で試したところ、50問以上質問した挙げ句に正解を出せず、アキネーターは敗北を認めました。こういうこともあるわけですが、もっと一般に知られている俳優やアイドルなら、ずっと少ない質問数でズバリ言い当ててきます。

https://blog.goo.ne.jp/hetare88888/e/60d6b781964383841ca59b6e904e7a22
「IF~THEN~(もし~なら~)」構造の知識ベース
もう少しシンプルな例でエキスパートシステムの知識データベースの仕組みを説明しましょう。
動物の種類を推論するシステムがあり、人間と以下のようなやりとりをしたとします。
ES「脊椎動物ですか」
人「はい」①
ES「海棲動物ですか」
人「いいえ」②
ES「卵生ですか」
人「はい」③
ES「翼はありますか」
人「いいえ」④
ES「変温動物ですか」
人「いいえ」⑤
ES「乳を出しますか」
人「はい」⑥
ES「カモノハシですね」
人「正解!」
この例では、①の問答で「もし脊椎動物なら、魚、クジラ、鳥、は虫類、両生類、哺乳類」というデータを適用、軟体動物や昆虫などが除外されます。②で「もし海棲動物なら魚、クジラ」、「もし陸棲動物なら鳥、は虫類、両生類、哺乳類」が適用され、魚とクジラを除外。③で「もし卵生なら鳥、は虫類、両生類」が適用され、哺乳類を除外。④で「もし翼があれば鳥」を適用、翼なしなので、は虫類か両生類になります。ところが⑤で「変温動物ではない」と来ます。ということは、は虫類でも両生類でもない。そこでESは「乳を出すか」確認。「はい」なので、ESは哺乳類で唯一卵生の単孔類・カモノハシに到達しました。
単純化していますが、エキスパートシステムの仕組みはだいたいこんな感じです。

http://www.seibutsushi.net/blog/2008/02/386.html
このようなエキスパートシステムは、あえて汎用性を抑え、医療や法律、財務会計など特定の狭い分野に特化することで、定式化しにくい「人間の常識」の必要性を回避し、逆に使いやすくなっています。1990年代までには、フォーチュン500の企業の3分の2が、ビジネスにエキスパートシステムを取り入れています。かなり複雑な観測と判断が必要で、専門家でさえ苦労するようなケースであっても、最終的な1つの答えではなく、確率的に推奨できる選択肢を提示することができるシステムが多くなっています。
エキスパートシステムの問題点
エキスパートシステムによって、人工知能が現実世界の具体的問題にかかわり、解決策を提示できるようになったことは大きな前進でした。しかし、1980年代も後半になると、技術的な問題や経済財政上の問題から、人工知能の発展は頭打ちになりました。
その問題は、前述の「アキネーター」の例に実は示唆されています。筆者が試したアキネーターはロケットニュース24の佐藤記者を言い当てることに失敗しました。筆者は、自分が知る限りの佐藤記者についての知識で、アキネーターの質問に正直に答えています。にもかかわらず言い当てられなかったのは、「データ不足」のためです。アキネーターは、佐藤記者についての十分な情報を持っていなかったのです。
ここで筆者がどのようにして佐藤記者の情報を得てきたかを振り返ってみます。それは「佐藤記者が書いた記事を数多く読んできたこと」に尽きます。同メディアの記者たちは記事に頻繁に「顔出し」しますので、佐藤記者についても「眼鏡をかけている」、「ボサボサの髪型で、はげてはいない」、「あまり太っていない」など風貌がだいたいわかります。また記事の内容から「40歳代である」、「喫煙者である」、「ポールダンスという運動をしている」などといった属性がわかります。
「人間」はこうして知識を得ます。しかし前述のアキネーターは、まだディープラーニングを実装していないのでしょう。佐藤記者のデータをインプットしてもらえていなかったのです。
つまり、1980年代までのエキスパートシステムにとって、最大の技術的問題点は「知識データは人間が入力してやらなければならない」ということでした。アキネーターの例でも、おそらく、筆者が勝利したことはアキネーターの運営スタッフ(人間の)に報告され、すぐに佐藤記者のデータを入力したことでしょう。
これと同じように、ある専門分野に応用するエキスパートシステムを作るには、コンピュータ技術者とは別にその分野の専門家、それも非常に優秀な専門家を必要とし、さらに分野によっては膨大で複雑になることもある知識を、ほぼ人力でAIに「教えて」あげなければならなかったのです。
このことはエキスパートシステムAIの運用をめぐる財政上の問題を招きます。時間が経つにつれて内容を更新しなければならないデータベースも、分野によってはありえます。このようなデータベースにもとづくエキスパートシステムは、維持・運営に人件費がかかります。時として、それは膨大な金額にふくれ上がります。この問題は、欧米の政府機関によるAI研究への資金供給カットにつながりました。
また、日本の第五世代コンピュータプロジェクトも、当初の目標を1つも達成することなく、1991年に終了しました。
こうした技術的な問題と経済的な問題に加え、AI開発に向いたLISPプログラム専用コンピュータが生産されなくなるという悪材料も重なりました。ふつうの安価な汎用パーソナルコンピュータの性能が向上し、高価なLISP専用コンピュータが売れなくなり、生産中止になったのです。
こうして、第2次AIブームは終わり、AI冬の時代がふたたび訪れました。
次の記事では、第2期・冬の時代に触れます。